「ペット可の物件を選ぶのって、こんなに大変だとは思わなかった…。」
私は9回の引越しを経験しましたが、ペット可物件を探すときは本当に苦労しましたし、怪しい不動産屋に引っかかりそうになったこともあります。
この記事では、私の経験をもとに「失敗しない物件選びのポイント」を詳しく解説します!
他にも「不動産選びの失敗しないコツ」や「アパート選びの失敗しないコツ」を記事にしています。 ご参考ください。
✅これからアパートを探す予定の方。 ✅ペット可の物件を探してる方。 ✅不動産選びのコツを知りたい方。
① 物件探しの苦労
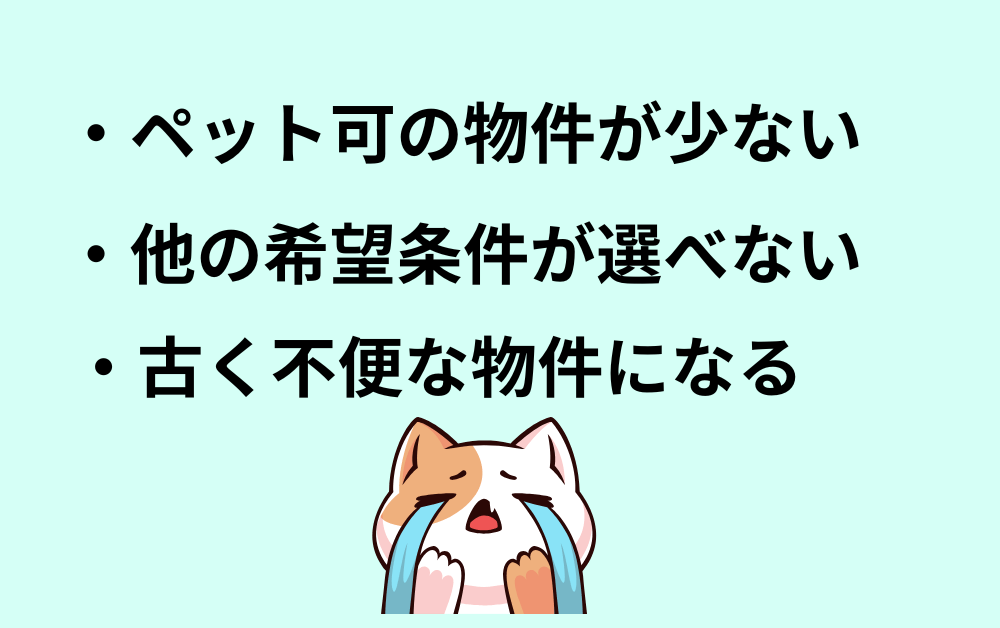
ペット可物件のお部屋探しは普通の物件とは違って、探す事自体が難しいことを知っておかないと本当に苦労します。
次に詳しいペット可物件の内容と対策を解説します。
ペット可の物件が少ない

ペットを飼える賃貸物件は、普通の物件と比べて圧倒的に数が少ないです。おおよそですが、普通の物件の10分の1と考えた方がいいです。
✅ペット可物件は競争率が高く、なかなか希望条件に合うものが見つかりにくい。 ✅都心部はもちろん、地方でもペット可物件は本当に少ない。 ✅繁忙期はペット可物件はすぐになくるので、物件を探すのに苦労する。
物件によっては、「猫はいいけど、犬はダメ」や「犬は小型犬のみ」など条件が違うので、入居条件を確認して選ばないといけません。
私の経験になりますが、犬よりも猫の方が物件数が多いです。
🔶猫は爪研ぎを壁にしても入居者が弁償すればいいので、大家さんの手間がない。 🔶犬はほえて近隣住民の迷惑になる可能性があるので、犬の入居は認めていない。 など
結構犬は入居自体が厳しいですが、小型犬は比較的入居しやすいです。中型犬や大型犬は入居がもっと困難になります。
他の希望条件が選べない

全ての希望条件は叶える事ができないと考えたほうがいいです。
私は「ペット可」と「洗濯乾燥機が置けること」を希望条件にしていましたが、築年数が古い物件ばかりで、築年数が新しい物件を探すのが難しかったです。
古く不便な物件になる

人気なエリアや便がいい所は、皆んなが住みたいと思っているため、費用がかかってしまうペット可物件ではなく、普通の物件にした方が不動産の利益が高くなります。
そうなると必然的にペットか物件は築年数が古い物件や不便な物件が多くなります。
引越しを何回もしていますが、ペット可物件は古いアパートだったり、駅から遠く不便な所でした。
▶ 対策
- 不動産会社に直接相談する:ネット上に掲載されていない物件情報を持っていることもあります。一つの不動産だけではなく、最低でも3か所の不動産を回る事が大事です。
- 「ペット相談可」の物件も候補に入れる:交渉次第では許可が下りる場合があるので、物件数は多く検討した方がいいです。
- エリアを広げて探す:自分が住みたいと思っている場所だけではなく、その周辺などエリアを広げる事でペット可物件の選択肢が増えることがあります。
- ペット可以外の希望条件を妥協する:ペット可の条件は外せないと思うので、他の希望条件を違う希望条件に妥協するか、他の希望をなしで物件を探すと物件が増える事があります。
②費用面の苦労
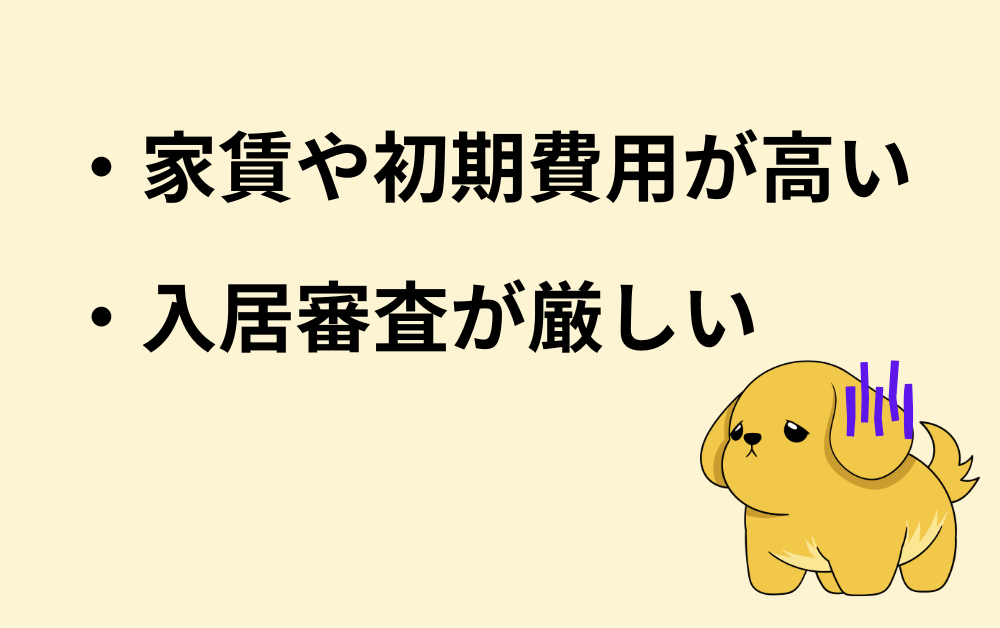
ペット可物件は普通の物件とは違って敷金や退去費用が高く、入居条件も厳しいので、本当に苦労します。
次に詳しいペット可の費用面の苦労の内容と対策を解説します。
家賃や初期費用が高い

ペット可物件は、通常の物件より家賃や敷金が高めに設定されていることが多いです。
ペットによる破損・汚損のリスクを考慮し、敷金が「追加1ヶ月」や「追加2ヶ月」などと設定されるケースも多いです。
🔶私は内見に行った不動産で「22万かかる」、「40万かかる」と言われた事がありました。 🔶以前住んでいた物件を退去した時は、退去費用を聞いていたので、多額のお金を追加で支払う事はなかったです。
退去費用は絶対に聞いた方がいい内容です。
これは私が不動産から聞いたペット可物件の話ですが、大型犬1匹と住みたいとアパートを契約した人がいたみたいですが、敷金3ヶ月、退去費用約2か月かかるという条件が不動産から出て、入居したそうです。大型犬と一緒に住む部屋は本当に少なく、古いマンションか、一軒家しかないので、値段も高くなるとのことでした。
▶ 対策
- 契約内容をしっかり確認し、退去時の負担を減らす工夫をする:入居する前に退去費用を確認し、多額の退去費用を請求される物件は避けた方がいいです。
- 入居時の初期費用が少しでも安くなるか交渉する:火災保険や鍵交換は安く対応してくれる所に変更するなど、初期費用を少しでも安くなるように動いた方がいいです。安心サポートなどと言ったサービスは使う事がないので、必要ありません。
入居審査が厳しい

ペット可物件であっても、大家さんが審査を厳しくすることがあります。「本当にペットの管理ができるのか?」を見られるため、審査に通らないケースもあります。
しつけや飼育歴がら長いことを説明することはもちろんですが、絶対聞かれることは、狂犬病ワクチンなどの予防接種を定期的に打っているかです。
狂犬病の予防接種以外にも6種などの予防接種を打つことが条件になることもあります。
どうしても予防接種しないと入居できない事が多いので、内見前に何の予防接種の証明が必要か聞いた方がいいです。
▶ 対策
- ペットのしつけ状況を説明できるようにする:無駄吠えがほとんどない事や外出時・室内のペットの様子を知らせることで、自分のペットが他の人に迷惑をかける事はほとんどない事をアピールするといいです。
- ペットの健康診断書やワクチン接種証明を用意する:万が一愛犬・愛猫が狂犬病以外の予防接種ができない時は動物病院で診断書を書いてもらうと、貸主が希望している予防接種をうたなくても入居できる場合があります。
- 飼育歴を伝えて、責任感があることをアピールする:飼育歴が長いと信用してくれます。飼育環境をきちんと伝えていくといいです。
③近隣トラブルの可能性
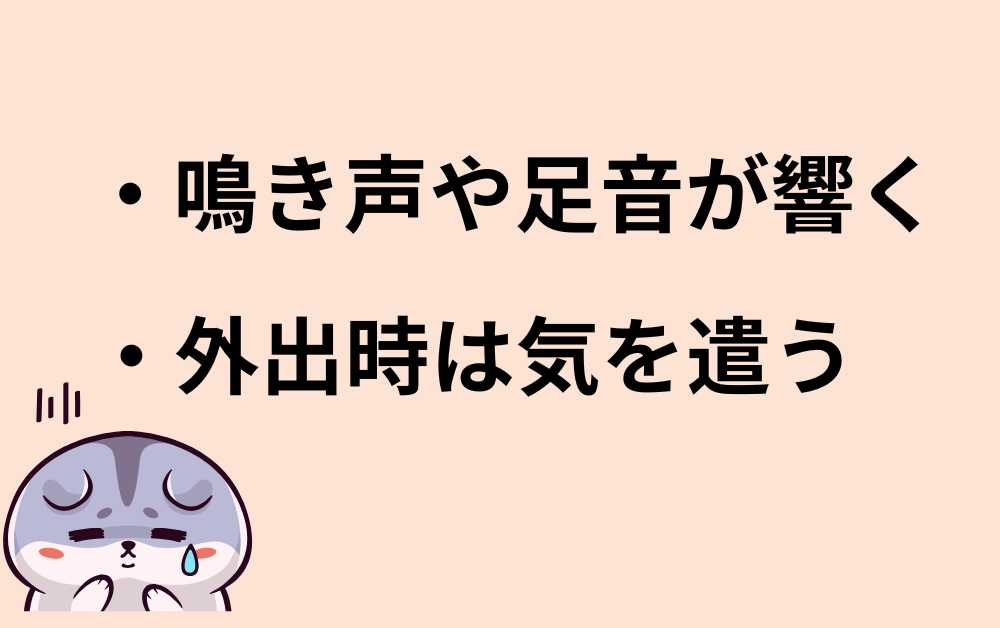
ペットの鳴き声や、共用スペースの使用マナーなど、周囲とのトラブルが発生する可能性もあります。
次に近隣トラブルの苦労の内容と対策を解説します。
鳴き声や足音が響く

無駄吠えがないようにしつけするなど対策が必要です。
騒音を防ぐためにコルクマットを敷いており、足音で響く事がなくなりました。 コルクマットは騒音予防もそうですが、犬がフローリングで滑る事がなくなるのでおすすめです。
コルクマットはいろんなものがありますが、おすすめはこちらです。
私は愛犬がいつもいる所にこのコルクマットを敷いていました。
基本的にコルクマットを敷くなど自分ができる騒音対策をしておけば、トラブルを未然に防げます。
▶ 対策
- 無駄吠え防止のしつけをする:入居前に躾けておけば、入居がしやすくなります。
- 防音マットやカーペットを敷く:防音できればなんでも大丈夫ですが、コルクマットがおすすめです。
- 夜間の騒音を防ぐために、遊ぶ時間を調整する:夜よりも日中遊ぶなど工夫しましょう。
外出時は気を遣う

最初からペットを飼うために作られた物件の場合は、ペットを飼っている人が多く、比較的トラブルになる事は少ないです。
しかし、物件が古くなるなど途中からペット可物件にした物件は、ペットを飼っている人が少ない可能性があり、すべての住人がペットが好きとは限りません。共用部分でのマナーが悪いと、苦情の原因になります。
会ったら挨拶をするなど、人としてのマナーを守っていれば、基本時にトラブルは防げます。近隣住民と密に関わる必要はありません。
▶ 対策
- エレベーターや廊下ではリードを短く持つ:共有部分の場所の場合は、他の人に愛犬が怪我をさせないために、対策していく事が大事です。
- 排泄物の処理を徹底する:近所を散歩する時は必ず排泄物の処理は怠らないようにする事が大事です。
- 近隣住民への挨拶を欠かさず、関係を良好に保つ:深く付き合う必要はありませんが、人としてのマナーは守るようにしていく事が大事です。
室内の傷・汚れ問題

騒音防止と重複してしまいますが、コルクマットを敷く事で床の傷は防ぐ事ができます。
壁については保護シートを貼れたら貼った方がいいですが、アパートやマンションの壁の状態で貼れないこともあります。
不動産に保護シートを貼れるか確認した方がいいです。
壁紙保護シートを買いましたが、入居するアパートの壁が保護シートを貼っても剥がれてしまう壁だったので、本当に無駄な買い物をしてしまいました。
汚してしまったら、定期的に掃除していけば、大きく汚れる事がないので、修繕費を考えるならば、こまめに掃除した方がいいです。
▶ 対策:
- 壁には保護シートを貼る(100円ショップなどで簡単に手に入る):ただし、貼れるか不動産に確認する事が大事です。
- 床にはカーペットやクッションフロアを敷く:床の傷をつけない工夫をする事が大事です。
- トイレのしつけを徹底し、粗相対策をする:しつけしても粗相した場合は、すぐに掃除する事が大事です。
まとめ
ペット可物件での生活は、思った以上の苦労があります。しかし、しっかりと準備をして対策を講じれば、快適な暮らしを実現できます。これからペットと賃貸生活を始める方は、ぜひ今回のポイントを参考にしてみてください!
あなたとペットの生活が素敵なものになりますように!
応援しています。
もしこの記事がいいと思ったら、コメントや他の記事も読んでくれると嬉しいです。
「自分と未来は変えられる!」
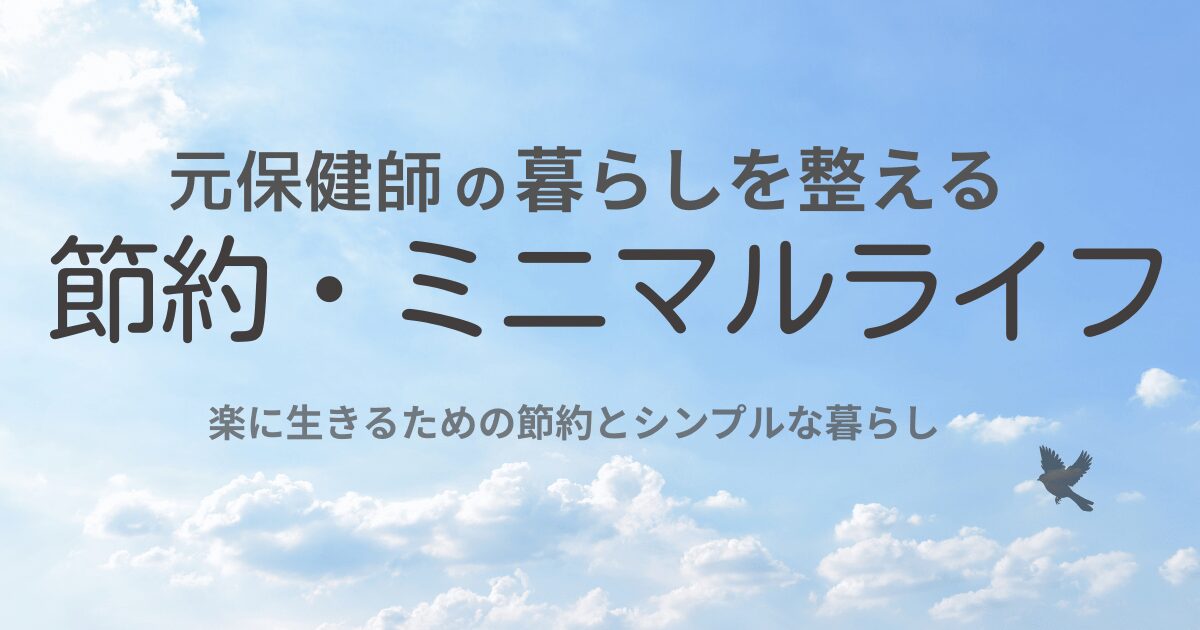
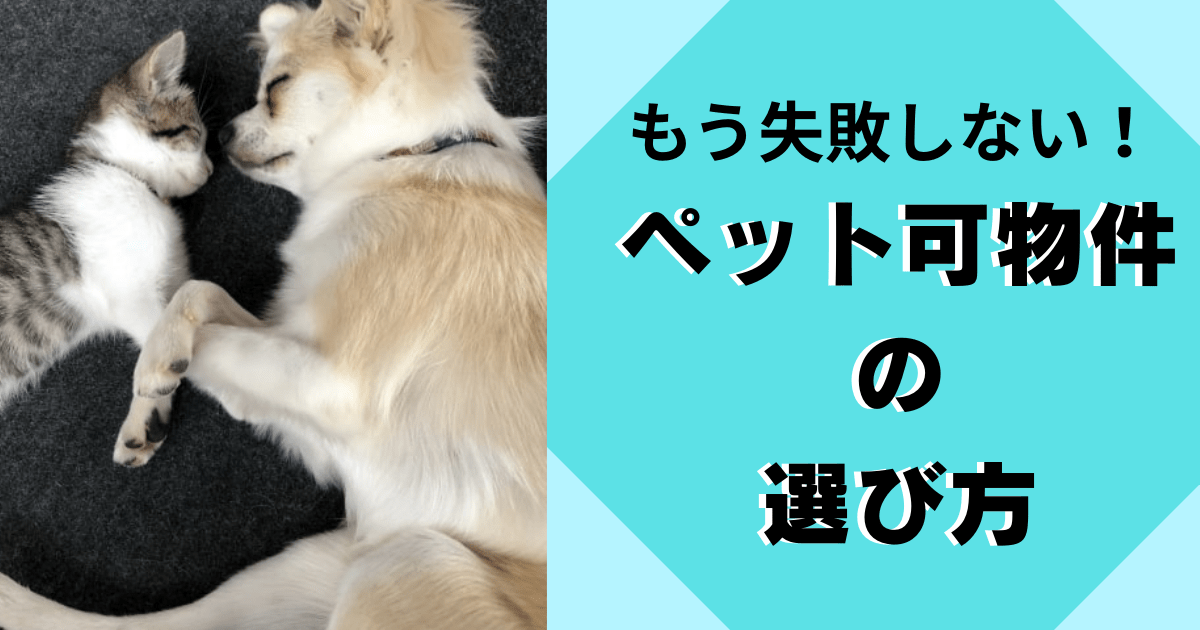
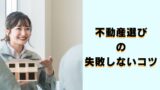
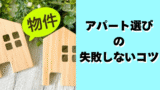
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4705ad6f.3b226618.4705ad70.47901a5e/?me_id=1201643&item_id=10000983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasia-kobo%2Fcabinet%2Fitem100%2Ftwcm-e01-018p.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント